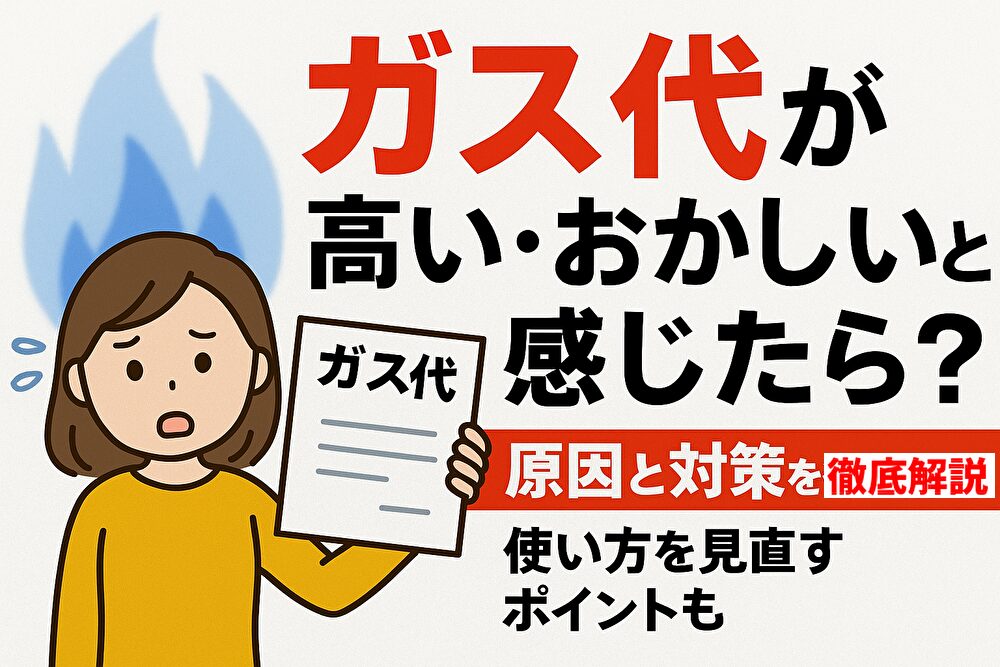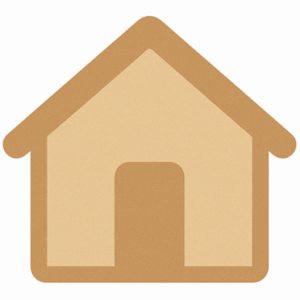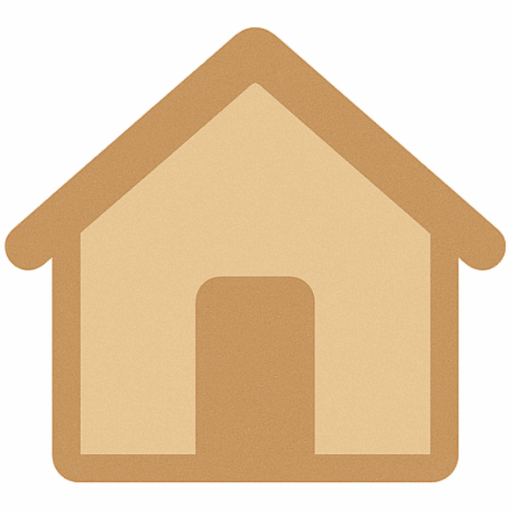「先月よりガス代が高い」「使い方は変えていないのに請求が増えた」——そんな疑問を抱いたことはないでしょうか。
家庭のガス料金は、使用量と単価の組み合わせで決まります。しかし、実際に“おかしいほど高い”と感じる場合、その多くは使い方や環境によるものです。
現役のガス会社社員として多くの問い合わせを受けてきましたが、「メーターの故障」「請求の間違い」といったケースは、考えにくいのが実情です。
実はガスメーターというのは国の「計量法」に基づいて厳格に製造・検査されており、検定に合格しているものだけが設置されています。
つまり、「メーターがおかしい」というのは、現実的にはほとんど起こりえないのです。
では、なぜガス代が高くなるのか。
その答えは、「使用量が増える条件が揃っている」からです。
特に給湯器やガスストーブなど消費量の大きい器具を長時間使用している場合や、外気温の低下によって給湯効率が下がっている場合など、気づかないうちにガスの消費が増えていることがあります。
この記事では、実際に現場で寄せられる「ガス代が高い」という相談をもとに、使い方・環境・機器の状態という3つの視点から原因を整理し、家庭でできる改善策をわかりやすく解説します。
ガス代が高いと感じる原因は?実際に多いパターン

ガス料金が高くなる背景には、ほぼ例外なく使用量の増加があります。
「前月と同じように使っているのに料金が上がった」と感じても、環境条件が変わっているケースが多く、実際には“おかしい”わけではありません。
ここでは、現場で特に多い事例を整理します。
1. 給湯器の使用量が増えている
家庭でガスを最も多く使うのは給湯器です。
お湯を沸かすには水の温度差を埋めるだけの熱エネルギーが必要ですが、冬は水温が低下するため、同じ湯温設定でも消費ガス量が大きくなります。
たとえば、夏場の水温が25℃で設定温度が40℃の場合、上げ幅は15℃ですが、冬に水温が5℃まで下がると上げ幅は35℃になります。単純計算でお湯づくりに必要なガス量は2倍以上になるのです。
この「水温差によるガス使用量の増加」は、特に11月〜3月にかけて顕著に現れます。
また、追い焚き機能を頻繁に使う家庭では、浴槽内の温度維持にも継続的なガス消費が発生します。
お風呂の保温を長時間行うと、ガス代は1日あたり100〜200円程度増えることも珍しくありません。
2. 暖房機器(ガスストーブ・セントラル)の稼働時間が長い
冬場はガスストーブやセントラル暖房の使用が増えることで、ガス代が急上昇するケースがあります。
特にFF式ストーブなどは広い範囲を暖められる一方、連続燃焼で1時間あたり0.2〜0.3㎥のガスを消費します。1日8時間稼働させれば、1か月で60〜70㎥に達することもあり、給湯と暖房の併用で請求額が大きく変わります。
暖房は快適性を左右するため、無理な節約は推奨できませんが、就寝前や外出時に自動OFFタイマーを活用するだけでも、月1,000〜2,000円の節約につながります。
またハイブリッド式のエコジョーズなどが設置されている場合は、本格的な冬前であれば電気で暖房をつける方が賢い選択でしょう。
3. 「使い方は変えていない」のに高くなる“環境要因”
「特に長風呂していないし、料理の回数も変わらない。それなのに高い」という声もよく聞かれます。
このような場合、多くは上記の外気温の低下による給湯効率の変化や、室内の暖房需要の上昇が影響しています。
給湯器は外気温が下がると燃焼時間が長くなり、機器が発生させる熱損失も増えます。
また、浴室・台所の換気時間が長い場合も、室温低下により湯張りやシャワーの使用時間が延び、結果的に使用量が増えることがあります。
このように、「いつもと同じ使い方なのに」というのは、環境が変わったことで同じ結果を得るためのエネルギーが増えているという構図です。
✅ ガス代が高くなる主な実要因
- 外気温の低下による給湯効率の悪化
- 給湯器・暖房機器の長時間使用
- お湯の使用回数・時間の増加
- 浴槽の追い焚きや保温の頻度
- 生活リズム・在宅時間の変化
こうした要素を見直すことで、ガス代の上昇には必ず理由があることがわかります。
「おかしい」と感じたときこそ、まずは“自分の使い方”と“環境条件”の変化に注目することが最も確実な判断材料になります。
自分の使い方を見直す前に確認すべき3つの基本ポイント

ガス代が「おかしい」と感じたとき、多くの方は「節約」や「業者への相談」をすぐに考えがちです。
しかし、まず行うべきは“料金の中身を確認すること”です。
ガス料金は感覚ではなく、明確な計算式と制度に基づいています。
数字を正しく読み取れば、ほとんどの疑問は解消できます。
ここでは、ガス代を見直す前に確認すべき3つの基本ポイントを解説します。
1. 「使用量(㎥)」の増減を確認する
料金の増減を判断するうえで最も重要なのが「使用量(㎥)」です。
請求書や検針票には必ず記載されており、ここが増えていれば料金が上がるのは当然の結果です。
特に給湯・暖房にガスを使う家庭では、外気温が低くなる冬場に使用量が2〜3倍に増えることもあります。
「先月と同じ使い方をしているのに高い」と感じる場合でも、実際には外気温の低下で給湯器の燃焼時間が長くなっているなど、使用環境による消費増が起きていることがほとんどです。
また、ガスメーターは国の計量法に基づいて厳密に製造・検査されています。
冒頭でも触れましたが、メーターの不具合で請求が増えることは実質的にありません。
使用量が増えているということは、それだけガスを使っているという事実に他なりません。
2. 原価調整額(燃料費調整制度)の影響を確認する
ガス料金は、「基本料金+従量料金(使用量×単価)」という構造で成り立っています。
このうち従量単価は、都市ガス・LPガスともに契約時に定められた単価が基本的に維持されます。
月ごとに変動するのは「原価調整額」であり、原油価格や為替レートの変動を反映させるために設けられている制度です。
たとえば、世界的に原油価格が上昇した月には、数十円〜数百円単位で原価調整額が上乗せされることがあります。
この調整は各社の契約約款に基づいて自動的に行われるため、不正な値上げではありません。
「単価が上がったように見える」という声の多くは、実際にはこの原価調整額の増加によるもので、契約上は正しい請求です。
💡 確認のポイント
- 明細書に「原価調整額」「燃料費調整額」などの項目があるかチェック
- 前月比で100円〜300円程度の変動なら、原価調整額の影響と考えてよい
- 長期的に高止まりしている場合は、ガス会社の単価設定自体を見直すタイミング
3. 基本料金と契約内容を整理する
ガス料金のもう一つの柱が基本料金です。
この中には容器の維持費や供給設備の維持及び点検、24時間監視体制、LPガスであれば配送などのコストが含まれており、LPガスでは地域によって若干の差が生じます。
一方で、都市ガスは公共料金として認可制であり、料金体系は事業者ごとに明確に定められています。
つまり、ガス会社が「勝手に料金を変える」ということはありえません。
明細書には必ず料金構成が記載されているため、不明点があればガス会社へ確認するのが確実です。
✅ ポイント整理
- ガスメーターは国の検定制度下にあり、基本的に過剰請求は考えにくい。
- 毎月の料金変動は「原価調整額(燃料費調整制度)」が主な要因。
- 基本料金や単価は契約時に明示され、勝手に変更されることはない。
この3つを確認すれば、「なぜ高くなったのか」は数字で必ず説明できます。
感覚的に「おかしい」と思っても、ほとんどの場合は使用量の増加または原価調整額の影響が原因です。
ガス代を上げてしまう“意外な使い方”

ガス代が高くなったと感じるとき、その多くは「特別なことをしていないのに請求が増えている」という声から始まります。
しかし実際には、日常の使い方の中に“気づかない無駄”が潜んでいることがほとんどです。
現場の経験から言えば、節約術よりもまず「どう使っているか」を見直すことが、最も確実な改善策になります。
1. シャワーの出しっぱなし・温度設定の上げすぎ
家庭で最もガスを使うのは、給湯器です。
特にシャワーの出しっぱなしは、1回の入浴で数十リットル単位の無駄が発生します。
加えて、外気温が下がる冬場は水温が低いため、同じ湯温にするにも燃焼時間が長くなり、使用量が自然に増えます。
また、給湯温度を42〜43℃など高めに設定している家庭では、燃焼量が大きくなり、わずか数度の違いでもガス代が1〜2割増えることがあります。
💡 改善のヒント
- シャワーは必要なときだけ流す
- 給湯温度は40℃前後を基本に設定
- 節水シャワーヘッドの利用でガス代・水道代ともに節約可能
2. 追い焚きや保温を長時間続けている
自動保温や追い焚き機能は便利ですが、給湯器が断続的に燃焼を繰り返すため、実はガス消費量が増える使い方です。
とくに冬は浴槽のお湯が冷めやすく、保温を長時間続けると1日あたり数百円単位の差が出ることもあります。
💡 改善のヒント
- 保温より「追い焚き1回」に切り替える
- 家族が続けて入浴すれば燃焼回数が減る
- フタを閉めることで保温効果が高まり、放熱ロスを軽減できる
3. ガスストーブや床暖房の長時間運転
暖房用のガス機器は、他の家電に比べてもガス使用量が多い設備です。
特にFF式ガスストーブは部屋をしっかり暖められる分、長時間連続で使えば月の使用量が大きくなります。
1日中つけっぱなしにしていると、暖房だけで1〜3万円前後のコストがかかるケースも珍しくありません。
このため、外出中や就寝時の運転を控えるだけでも効果的です。
FF式は安全性の高い機器ですが、コスト面では最も影響の大きい器具のひとつといえます。
💡 改善のヒント
- 就寝前や外出時はOFFにする
- タイマー運転を活用して自動で消す
- 室温を上げすぎず、湿度を保つことで体感温度を高める
4. 給湯設定のこまめな変更や、短時間の再点火
「ぬるい」「熱すぎる」と感じて温度設定を頻繁に変えると、そのたびに再燃焼が起こり、わずかずつですがガス消費が増えます。
また、シャワーを途中で止めて再開するときにも再点火が発生し、これも積み重なれば無視できない差になります。
💡 改善のヒント
- 季節に合わせた設定を最初に決め、頻繁に変えない
- 冬場は一度に十分な温度に設定しておき、再調整を減らす
✅ ガス代を上げやすい行動まとめ
- シャワーを出しっぱなしにしている
- 追い焚き・保温を長時間続けている
- ストーブをつけっぱなしにしている
- 給湯温度をこまめに上げ下げしている
- 入浴時間や家族の使用時間がバラバラになっている
ガス代が高くなる原因の多くは、機器の性能ではなく「使い方」にあります。
たとえ高効率の給湯器やストーブを使っていても、使い方次第で消費量は簡単に数割変わります。
逆に言えば、器具を買い替えずに節約効果を出すことも十分可能です。
設備を買い替えずにできる“ガス代の見直し術”

ガス代を抑えるには、給湯器やストーブを最新機種に交換することも一つの方法ですが、それ以前に「いまある設備でどれだけ効率的に使えるか」を見直すほうが先決です。
現場で点検を行っていると、使い方や環境を少し工夫するだけで、月に何千円も節約できる家庭は少なくありません。
ここでは、設備を買い替えなくてもできる現実的な見直し策を紹介します。
1. 給湯器の“温度設定”を季節に合わせる
給湯器の設定温度は、夏場と冬場で適切な範囲が異なります。
一般的に、夏は37〜40℃、冬は40〜42℃が目安ですが、多くの家庭では冬になると無意識に高めの温度を維持したままにしている傾向があります。
外気温が下がると給湯効率が落ちるため、温度を上げすぎず、使用する時間を短くするだけでもガス消費を抑えられます。
また、シャワー時に熱すぎて水で薄めている場合、設定温度を1〜2℃下げるだけで燃焼時間が短くなり、年間で1,000円以上の差につながることもあります。
💡 実践のポイント
- 夏場は37〜40℃、冬場は40〜42℃を目安に
- 「ぬるい」と感じる時は水温低下の影響。設定よりも時間を調整
- 「熱い→水で薄める」は最も非効率な使い方
2. 風呂の「フタ」と「入浴タイミング」を活用
自動保温を長時間続けるより、フタをしっかり閉めるほうがはるかに効率的です。
浴槽の熱はフタを閉めるだけで約30〜40%の放熱を防げるといわれています。
また、家族が時間を空けずに続けて入浴するだけでも、追い焚きの燃焼回数を減らすことができます。
在宅時間がバラバラな場合でも、「夜は一気に入る」「朝はシャワーだけにする」といったルールを決めると、自然とガスの使用量が下がります。
💡 実践のポイント
- フタを閉めるだけで大きな節約効果
- 入浴はできるだけ時間を空けずに
- 自動保温より「追い焚き1回」で済ませる
3. ガスストーブの効率を上げる“部屋の工夫”
ストーブの燃焼効率を上げるには、部屋の暖まり方を見直すことが効果的です。
たとえば、窓からの冷気が強い部屋では、カーテンを厚手にしたり、窓際に断熱シートを貼るだけでも熱の逃げを防げます。
また、部屋が暖まるまでの時間を短縮できるため、燃焼時間も結果的に減少します。
さらに、サーキュレーターを併用して空気を循環させると、室温のムラが減り、体感温度が1〜2℃上がるといわれています。
これにより、設定温度を下げても同じ快適さを維持でき、結果的にガス使用量を抑えられます。
💡 実践のポイント
- 厚手のカーテン・断熱シートで熱を逃さない
- サーキュレーターで空気を循環させる
- 暖房の設定温度を1℃下げるだけで年間数千円の差
4. 給湯配管や蛇口まわりの点検も効果的
意外に見落とされがちなのが、給湯配管の断熱と蛇口の水漏れです。
特に屋外に配管が通っている場合、断熱材の劣化で熱損失が起きると、給湯器が必要以上に燃焼してしまいます。
また、蛇口のわずかな漏れでも、1日で数リットル、1ヶ月では数百リットル単位のロスになります。
💡 実践のポイント
- 屋外配管の断熱材が破れていないか確認
- 給湯器の周囲に障害物を置かない(通気・燃焼効率が下がる)
- 蛇口の閉まり具合を定期的にチェック
5. 「お湯を使う時間」を集中させる
家庭内で同時に複数の蛇口を開けると、給湯器が最大出力で燃焼するため、効率が落ちます。
朝の時間帯などで台所・洗面・浴室を同時に使う習慣がある場合、順番を少しずらすだけでもガス使用量を下げることが可能です。
また、夜の入浴と洗い物の時間を近づけることで、給湯器の待機損失を減らせます。
これは、使用の間隔を短くすることで機器内部の温度低下を防ぎ、再加熱までの燃焼時間を短縮できるためです。
✅ 設備を変えずにできる実践まとめ
- 給湯温度は「低め・短時間・一定」で使う
- フタや断熱対策で保温・暖房効率を上げる
- サーキュレーターで暖気を循環させる
- 配管の断熱・蛇口の点検を行う
- 給湯の使用時間を集中させ、再加熱を減らす
設備を買い替える前に、まずは「使い方」と「環境」を整えること。
それだけで多くの家庭では月に1,000〜3,000円、年間で1〜2万円の節約効果が見込めます。
高効率な給湯器を導入しても、使い方が非効率では本来の性能を活かしきれません。
毎日のちょっとした意識の積み重ねが、最も現実的で確実な節約策なのです。
よくある質問(FAQ)
Q1. ガス代が急に高くなったのですが、メーターが壊れている可能性はありますか?
A. ありません。
ガスメーターは国の「計量法」に基づいて製造・検査されており、、誤計測が原因で料金が上がることはまず考えにくいでしょう。
多くの場合、外気温の低下やお湯の使用時間の増加など、生活環境の変化が主な原因です。
Q2. 「使い方は同じなのに高い」と感じるのはなぜですか?
A. 水温・外気温の変化による燃焼時間の増加が主な理由です。
冬になると水道水の温度が下がり、給湯器はお湯をつくるためにより多くのガスを燃焼します。
同じ湯温設定でも、夏に比べて2倍近くのエネルギーを使うこともあります。
このため、使用パターンが変わっていなくても料金が上がるのは自然なことです。
Q3. 原価調整額って何ですか?ガス会社が勝手に上げているのですか?
A. 原価調整額は、原油や輸入価格の変動を反映するための制度です。
ガス会社が独自に料金を上げているわけではありません。
国際的な原料価格や為替レートの影響で、数か月遅れて反映される仕組みです。
値上がりが続く時期は、どの会社でも一時的に高止まりする傾向があります。
Q4. 節約のためにお湯の使用を減らしたほうがいいですか?
A. 無理に我慢するより、“効率的に使う”ことが大切です。
シャワーを短くする・追い焚きを減らすなど、燃焼時間を減らす工夫が効果的です。
また、給湯温度を40℃前後に保ち、夏と冬で設定を分けるだけでも年間1,000〜2,000円の違いが出ることがあります。
快適さを保ちつつ、使い方を工夫することが最も現実的な節約方法です。
Q5. ガス会社に相談してもいいのはどんなとき?
A. 請求内容に疑問があるときや、ガス機器に異常を感じたときです。
「明細の見方が分からない」「使用量が極端に変化した」「ガス臭がする」などの場合は、早めにガス会社へ連絡してください。
特ににおいや炎の異常があるときは、使用を止めて安全確認を依頼するのが基本です。
料金に関しても、検針票を見ながら相談すれば、丁寧な説明を受けられます。
まとめ:ガス代が高いと感じたときの考え方と行動
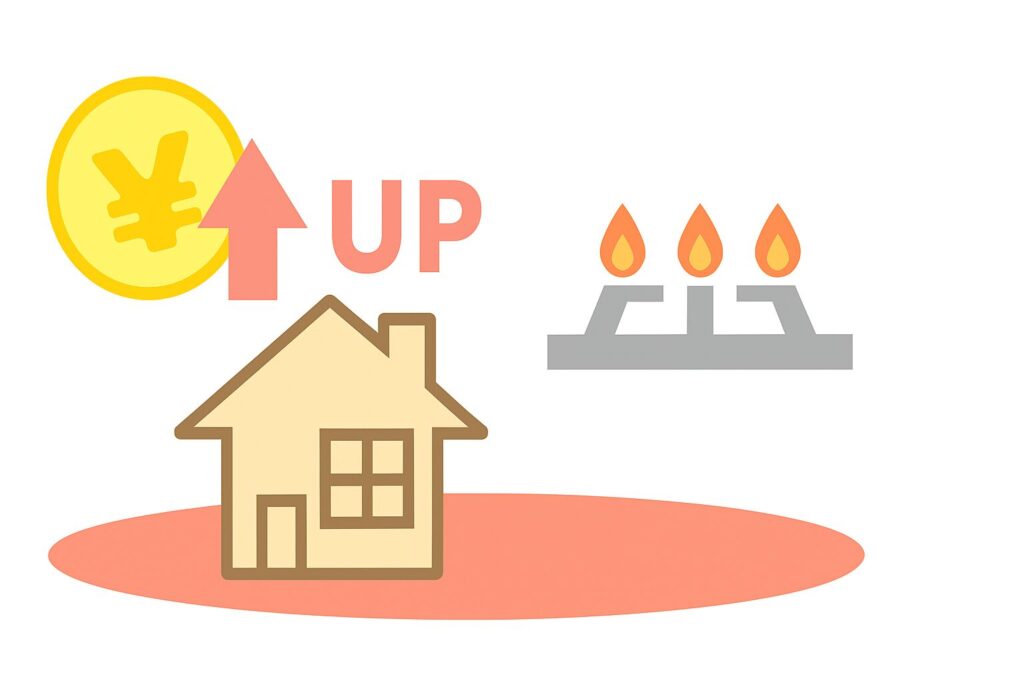
ガス代が思ったより高くなると、誰でも「おかしい」「請求が間違っているのでは」と感じてしまいます。
しかし実際の現場を見ていると、明細に誤りがあるケースはほぼ皆無で、原因の多くは「使い方」「季節」「環境」にあります。
ここまでの内容を踏まえ、家庭でできる判断と行動を整理しておきましょう。
1. まず“異常ではない”ことを前提に考える
ガスメーターは、国の計量法に基づいて厳しく管理されています。
そのため、メーターの誤作動や計量ミスで料金が上がることは、実務上ほとんどありません。
つまり、「おかしい」と感じるときも、まずは異常ではなく“理由がある変化”と捉えることが大切です。
季節ごとの外気温の変化や、家族の入浴時間・回数の増加、給湯器の燃焼時間など、
目に見えない“生活リズムのズレ”が料金に反映されている場合がほとんどです。
「使い方は変えていない」という言葉の裏には、実際には気温・水温・生活時間帯の微妙な変化が隠れていることが多く、
それがガスの使用量に直結しています。
2. 感覚ではなく“数字で判断”する
ガス料金の変化を感覚で判断するのは危険です。
検針票や明細にある「使用量(㎥)」を見れば、上昇の理由は明確に見えてきます。
もし前年同月より20〜30%以上増えている場合は、まず使用環境の変化を確認してみましょう。
また、過去の明細をお持ちであれば季節ごとの傾向が一目で分かります。
これを基に「自然な増加か」「使いすぎか」を冷静に判断できるようになります。
💡 数字で見るポイント
- 検針票の「使用量(㎥)」の推移
- 前年同月比の増減率
- ガス機器の使用時間や設定温度の変化
3. 節約よりも“効率”を意識する
ガス代を下げるには、我慢よりも効率の見直しが重要です。
「保温を短くする」「設定温度を下げる」といった工夫はもちろんですが、
実際には同じ快適さを保ちながら使用量を減らす工夫こそが長続きします。
たとえば、
- シャワーを止めるタイミングを意識する
- ストーブの風向きを調整して部屋を均等に暖める
- 給湯温度を季節ごとに見直す
これらはすべて、快適さを損なわずに燃焼時間を減らす方法です。
節約を目的にしすぎるとストレスが増え、結局元に戻る家庭も少なくありません。
「どうすれば同じ快適さで使えるか」を軸に考えると、無理なく継続できる節約につながります。
4. 「前年より高い=異常」ではない
毎年冬に「去年より高い」と感じる方が多いのは自然なことです。
その理由は、前年の外気温・水温・在宅時間・家族構成など、複数の条件が変わるからです。
特に寒い年は、給湯器の燃焼時間が数分単位で延び、その積み重ねが1か月分の使用量に大きく影響します。
また、在宅時間が増えた・浴室乾燥機を使うようになった・シャワー時間が長くなったなど、日常の変化も自然なガス増加の要因になります。
したがって、「前年より高い」だけでは異常とは言えません。
数字を確認し、どの要因が増加を招いたのかを見極めることが重要です。
5. 不安なときは“相談”より“確認”を
現場の経験から言えば、「料金が高い」と感じてガス会社に問い合わせた結果、実際に不具合だったケースはほとんどありません。
多くの場合、使用量や原価調整額を丁寧に説明すると納得されます。
不安を感じたときは、いきなりクレームを入れるのではなく、まずは手元の検針票を見ながら次の3点を整理してみてください。
- 今月の使用量(㎥)
- 前年同月の使用量
- 使用状況の変化(入浴回数・在宅時間など)
この3点を押さえたうえで相談すれば、
ガス会社側も具体的に説明しやすく、スムーズな対応が受けられます。
✅ 最後に:ガス代を“正しく理解”することが一番の節約
ガス代は、感覚ではなく数字と仕組みで決まります。
誤解や不安の多くは、「料金の成り立ちを知らないこと」から生まれています。
メーターの誤作動や不当請求といった事例は極めて稀で、ほとんどの場合は使用環境の変化や外気温の影響で説明できます。
正しく理解し、正しく使う。
それが、無理なく快適な暮らしを維持しながらガス代を抑える最も確実な方法です。
物価高の今だからこそ、「ガス代だけは放置しない」選択を
ガス料金が高いと思う今だからこそ、ぜひ一緒に見直しておきたいのがLPガスそのものの契約内容です。
LPガスの料金は各ガス会社で設定しているものなので、どこのガス会社が一番安いか知りたくはありませんか?
食費・電気代・日用品…
何もかも値上がりしている今、契約を変えるだけで下がる可能性がある支出を見逃すのは、正直もったいない選択です。
「長年同じ業者だから安心」=「料金が適正」とは限りません。
実際に見直した結果、年間1万円〜2万円以上安くなった家庭も多数あります。
実は今、無料・匿名感覚でお住まいの地域に合った適正価格のガス会社をまとめて比較・紹介してもらえる方法があります。
しかも
✔ しつこい営業なし
✔ 今の契約を無理に変える必要なし
✔ 合わなければ断ってOK
「安くなる可能性があるか」を確認するだけでも利用できます。
何もせずに高い料金を払い続けるより、まずは一度、今の料金が適正かどうかを確認してみませんか?
▼ 申し込みから切替までネットで完結【エネピ】

入力は最短1分
複数のLPガス会社を一括比較
面倒な交渉はすべてお任せ