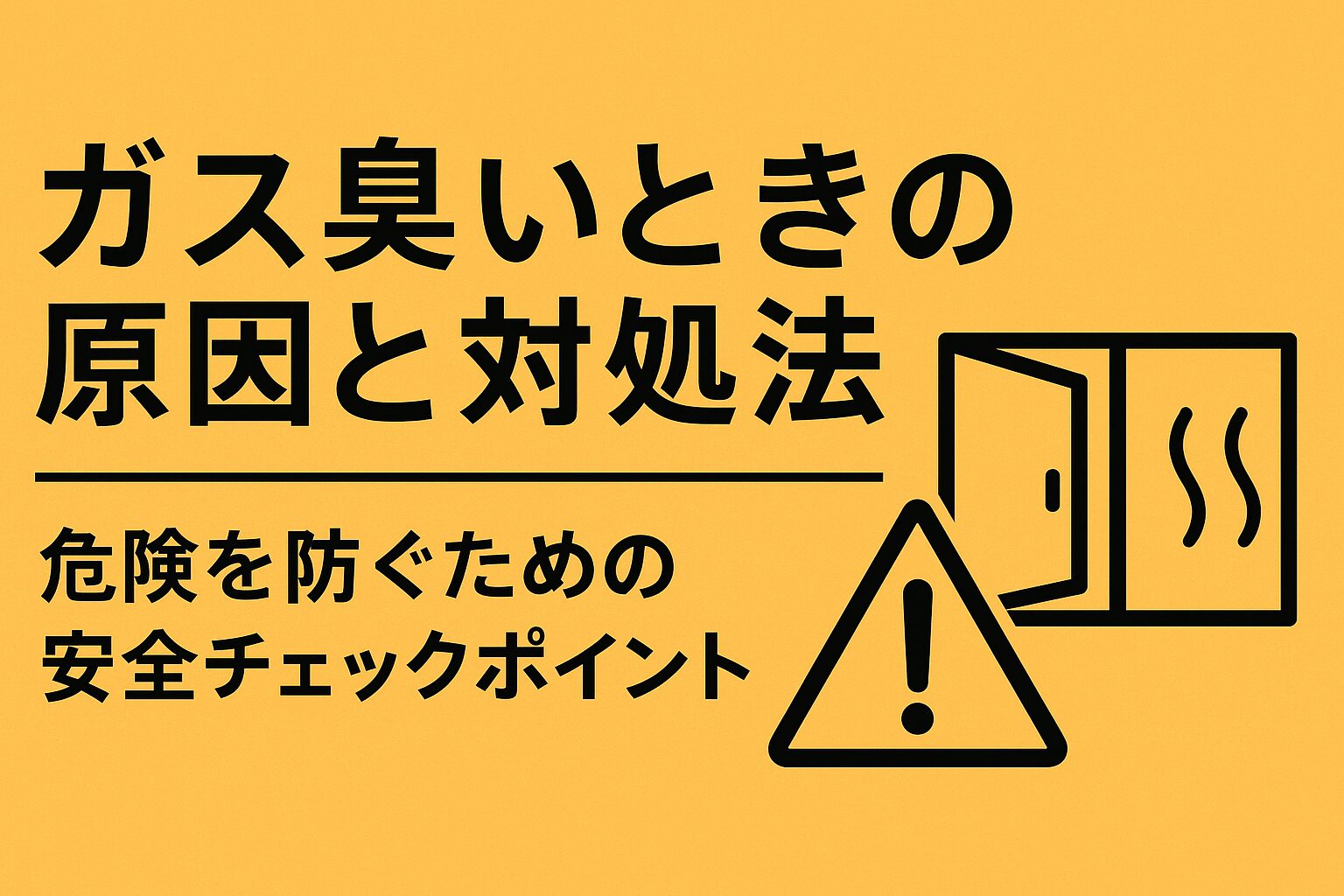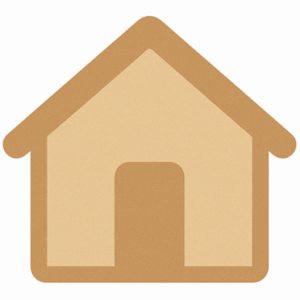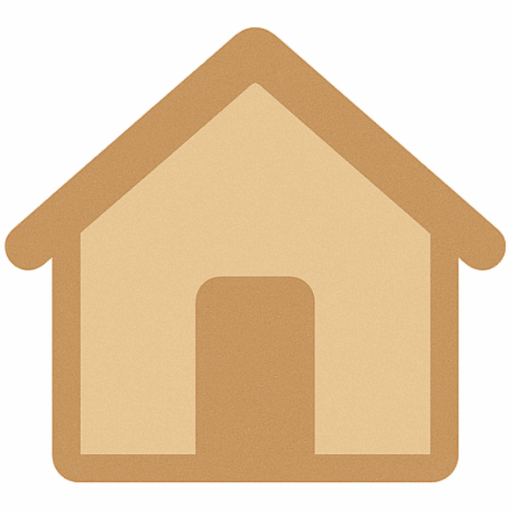お部屋の中で「なんだかガス臭い」と感じたとき、多くの方がまず思うのは「気のせいかな」「さっき火を使ったからかも」という小さな違和感でしょう。
しかし、ガスのにおいがするということは、燃焼ガスが室内に漏れている、もしくは供給系統で異常が起きている可能性を意味します。
特にガスは空気より軽いか重いかによって滞留する場所が異なり、適切な対応をしないと、知らないうちに危険な濃度まで溜まってしまうことがあります。
都市ガス(13Aなど)やLPガス(プロパンガス)には、無臭のガスに「付臭剤(メルカプタン)」が加えられています。
これは、漏れをすぐに気づけるようにするための安全措置です。
つまり、ガスのにおいを感じるということ自体が、すでに異常を知らせる“警告信号”なのです。
実際に、一般財団法人日本ガス協会が公表している「ガス漏れ時の対応」でも、においを感じた際は火気を使わず、換気と元栓の確認を落ち着いて行うよう呼びかけています。
においを感じたら、まずは安全確保を最優先に行動することが大切です。
(※一般社団法人日本ガス協会:ガス臭いと感じたら より)
このコラムでは、ガス臭いと感じたときの正しい対処法を、現役のガス会社に勤める著者が解説します。
ガス臭いときに最初にやるべきこと

ガスのにおいを感じた瞬間に最も大切なのは、火気を使わず、落ち着いて安全を確保することです。
焦って電気スイッチを操作したり、コンロを確認したりすると、わずかな火花で引火するおそれがあります。
行動の順番を守ることで、危険を最小限に抑えられます。
✅ 1. ガス会社に連絡する
→ ガス会社の緊急連絡先へ通報します(24時間対応)。
「においを感じた場所」「使用していた機器」「ガスの種類(都市ガスまたはLPガス)」を伝えると、迅速な対応につながります。
✅ 2. 火を使わない
→ コンロやストーブの使用はもちろん、ライターやマッチなどの火気も厳禁です。わずかな火種でも引火の危険があります。
✅ 3. 換気をする(窓やドアを開ける)
→ ガスを屋外に逃がすため、できるだけ多くの窓やドアを静かに開けます。
換気扇や電気スイッチには触れず、自然換気を行ってください。
LPガス(プロパンガス)は空気より重く、床付近に滞留しやすいため、低い位置の窓を優先的に開けるのが効果的です。
✅ 4. ガス栓・メーターの元栓を閉める
→ コンロや給湯器などの個別栓、屋外のガスメーター(バルブ)を閉め、ガスの供給を止めます。
構造が分からない場合や硬くて回らない場合は、無理に操作せずそのままにしておきましょう。
※ガス会社への連絡がつかない場合や、火災などの危険が差し迫っている場合のみ消防(119番)へ通報します。
💡 行動の優先順位
- ガス会社へ連絡
- 火を使わない
- 換気をする
- 元栓を閉める
においを感じたら、まず安全確保を最優先に。
判断に迷う場合でも、自己判断せずガス会社に相談することが最も確実です。
ガス臭の原因を見分けるポイント

ガスのにおいを感じたとき、原因をすぐに判断するのは難しいものです。
実際には、ガス漏れによるものだけでなく、燃焼の不具合や点火時の残留ガスなど、複数の要因で「ガス臭い」と感じることがあります。
ただし、どのような場合でも、においを感じた時点で“異常の可能性”があると考え、慎重に確認することが大切です。
🔍 主なガス臭の原因分類
✅ 1. ガス漏れ(配管・接続部の不具合)
→ ゴムホースや金属管の接続部が緩んでいる、または経年劣化しているケースです。
特にコンロの接続ホースは経年劣化で硬化やヒビ割れもしやすく、見た目に異常がなくても交換が必要です。
また、給湯器やストーブなどでも、長年の使用によって接続部やガス栓まわりが劣化し、稀に微量の漏れが生じることがあります。
✅ 2. 燃焼不良によるにおい
→ 炎が青ではなくオレンジ色や黄色に変わっている場合、空気不足やバーナーの詰まりによる燃焼不良が考えられます。
このときのにおいは、焦げ臭さや酸っぱい臭気を伴うことが多く、いわゆる「ガス臭」とは少し異なります。
✅ 3. 点火直後や消火後の残留ガス
→ コンロやストーブを点けた直後、一瞬だけにおいを感じることがあります。
これは正常な点火動作によるもので、短時間で消える場合は心配いりません。
ただし、においが長く残る場合や頻発する場合は点火系統の不良が疑われます。
✅ 4. 周囲からの流入・他機器の影響
→ 近隣の屋外給湯器や工事現場など、外部の排気が風に流されて入るケースもあります。
屋内の機器に異常がなくても、一時的に「ガス臭い」と感じることがあります。
📋 チェックのコツ
- 「いつ・どこで・どんな状況で」感じたかをメモしておく
- 点火前後や風向き、使用した機器を思い出すと原因の特定が早くなる
🧩 都市ガスとLPガスでの違い
| ガスの種類 | 主成分 | 空気との比重 | においの特徴 | 漏れたときの滞留位置 |
|---|---|---|---|---|
| 都市ガス(13A) | メタン | 約0.6(空気より軽い) | やや刺激のある軽いにおい | 天井付近にたまりやすい |
| LPガス(プロパン) | プロパン・ブタン | 約1.5(空気より重い) | 玉ねぎが焦げたような濃いにおい | 床付近にたまりやすい |
ガスの種類によって滞留しやすい位置が異なります。
都市ガスでは天井側、LPガスでは床近くを中心に換気することで、より早くガスを逃がすことができます。
また、ガス警報器の設置位置もこの比重に基づいており、都市ガス用は天井付近、LPガス用は床面近くに設置されます。
においが弱くても、連日同じ場所で感じる場合は漏れの可能性が高いため、使用を中止してガス会社へ相談するのが確実です。
家庭でできるのはあくまで観察まで。ガス臭がしたらガス会社へ、機器の分解や点検は必ず専門業者に任せましょう。
ガス臭いけど大丈夫な場合もある?

ガスのにおいを感じたら、まずは安全を最優先に行動することが鉄則です。
ただし、すべてのケースが「ガス漏れ」と直結するわけではありません。
中には、正常な燃焼や動作の一部として一時的ににおいを感じることがあり、慌てて使用を止める必要がない場合もあります。
ここでは、そうした“においがしても問題のないケース”を整理し、判断の目安をわかりやすく解説します。
🔹 点火・消火の瞬間に感じるにおい
ガス機器の多くは、点火の際にガスが一瞬だけ放出されます。
これはバーナー部に火が届くまでのわずかな間で発生するもので、正常な燃焼動作の一部です。
このときのにおいは軽く、数秒で消えるのが特徴です。
特にガスコンロやストーブの自動点火では、電極が汚れていると着火までの時間が少し延び、においがやや強く感じられることがあります。
💡 判断のポイント
- においが一瞬で消える
- 炎の色が青く安定している
- 連続使用でにおいが残らない
これらが当てはまる場合は、基本的に心配ありません。
ただし、においが残る・炎が不安定という場合は点火系統や空気量の調整が必要です。
🔹 新品または長期間未使用の機器で感じるにおい
新品のガス機器や、しばらく使っていなかった機器を初めて点けた際ににおいを感じることがあります。
これは、内部の防錆油や金属部品の保護剤が熱で焼けるにおいであり、ガス漏れとは異なります。
使用開始から数分〜数十分で自然に消えるため、換気をしながらしばらく運転を続けて問題ありません。
ただし、においが何日も続く・煙や異音を伴う場合は、燃焼不良の可能性があるため点検が必要です。
🔹 風向きや換気状態による一時的なにおい
屋外の給湯器やストーブの排気が風向きによって室内に入り込むと、ガスのようなにおいを感じることがあります。
特に冬場や無風状態では排気が滞留しやすく、窓付近やベランダで「ガス臭い」と感じるケースが多く報告されています。
この場合は、屋内のガス機器を止めてもにおいが続くかどうかを確認するのが有効です。
屋外でのみ感じる、または風向きによってにおいが変化するようなら、外部からの影響の可能性が高いと考えられます。
📋 においがしても危険ではない主なケース(まとめ)
- 点火・消火の瞬間(短時間で消える)
- 新品または長期間未使用の機器を初使用したとき
- 屋外の排気が風で戻ってくるとき
- 機器の清掃直後(わずかな残留ガスや油分の焼け)
これらはいずれも一時的なもので、通常は換気を行えばすぐに収まります。
しかし、においが長く続く・使用中ずっと感じる・以前より強くなったときは、異常の兆候です。
その際は迷わずガス会社に相談し、機器の使用を中止してください。
危険な臭いとそのサイン|すぐにガス会社へ連絡すべき状況

ガスのにおいには、点火時など一時的なものもあれば、危険を知らせる“異常のサイン”である場合もあります。
特に、においが持続する・強くなる・他の異常を伴うときは、自己判断で使用を続けるのは非常に危険です。
ここでは、ガス漏れや燃焼不良など、実際に事故につながる恐れがある状況を整理し、早急にガス会社へ連絡すべきサインを具体的に示します。
🔺 においが長時間消えない・特定の場所で常にする
ガスのにおいが長く残る、あるいは毎回同じ場所で感じる場合は、配管や接続部から微量な漏れが発生している可能性があります。
特に、ガスコンロまわりや給湯器のガス栓付近、床下や屋外メーターまわりでにおいが強いときは注意が必要です。
風通しが良い環境でもにおいが消えない場合、確実に何らかの異常があると判断して差し支えありません。
💡 行動の目安
- 同じ部屋・同じ位置で毎回におう
- 換気しても30分以上においが残る
- ガス栓付近から微かなシュー音がする
このような状況では、使用を止め、窓を開けて自然換気をしながらガス会社へ連絡してください。
🔺 火を使っていないのにガス臭い
調理をしていない、ストーブや給湯器を使っていない状態でにおいがする場合は、
機器以外(配管やガス栓まわり)からの漏れの可能性があります。
ありがちなのが供給設備のシリンダー(ガス)の残量が減ってきた時に、残ガス臭が室内に入る場合があります。
その際は臭いがするだけでガス漏れの心配はありませんが、本当に漏れている可能性も考えられるので、いずれにしてもガス会社へ連絡するのがいいでしょう。
またガスメーターのバルブ部分、ガスホースや金属フレキ、匂いがする場所などを確認し、無理のない範囲で把握しておくと、ガス会社が現場対応する際に原因特定がスムーズになります。
🔺 給湯器やストーブの排気口まわりが焦げ臭い・熱い
給湯器やFF式ストーブなどで「焦げたにおい」「異常な熱気」を感じる場合は、排気がうまく外に出ていない可能性があります。
ガス臭いとは別の話になりますが、排気口の詰まりや凍結、動物の巣などが原因で排気が逆流すると、燃焼が不安定になり非常に危険です。
また、排気筒の接続不良によって燃焼ガスが屋内に漏れると、無臭の一酸化炭素中毒につながるおそれもあります。
においがしなくても体調不良(頭痛・吐き気)を感じる場合は、ただちに使用をやめて換気・避難してください。
📋 すぐにガス会社へ連絡すべき状況(まとめ)
- においが長時間消えない、特定の場所で常にする
- 火を使っていないのにガス臭い
- においと同時に異音や炎の異常がある
- 排気口まわりが焦げ臭い、熱を帯びている
- ガスメーターやガス栓付近でシュー音がする
これらの症状はいずれも、自分で解決しようとすると危険な領域です。
安全のためには、機器の操作など行わず、ガス会社へ連絡して点検を依頼することが最善です。
少しでも「おかしい」と感じたら、その直感を信じて使用を止めることが、最も確実な安全対策になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. ガス臭いと感じたら、まず何をすればいいですか?
A. すぐに火気を使うのをやめ、まずはガス会社へ連絡をしましょう。その後、指示を仰ぎながら窓やドアを静かに開けて換気を行ってください。
電気のスイッチや換気扇には触れず、ガス栓やメーターの元栓を閉め、できる限り安全を確保した上でガス会社の到着を待ちましょう。
Q2. においが一瞬だけしたのですが、使用をやめたほうがいいですか?
A. 点火や消火の瞬間に一時的ににおいがする場合は、正常な動作であることが多いです。
ただし、においが長く残る・何度も同じ現象が起きる場合は、機器の異常が考えられるためガス会社へ相談してください。
Q3. ガス臭いけど、ガス漏れ警報器が鳴っていません。大丈夫でしょうか?
A. 警報器は濃度や風向きなど条件によって作動しないことがあります。
警報が鳴っていなくても、においを感じた時点で異常の可能性があります。
警報器の反応を待たず、すぐにガス会社へ連絡してください。
Q4. ガスのにおいが屋外で強くする場合、どうすればいいですか?
A. 屋外のガスメーターや給湯器、ボンベまわりでにおいを感じるときは、近づかずにガス会社へ通報してください。
LPガスの場合はボンベ周辺、都市ガスの場合はメーター付近での作業や確認も避けましょう。
安全を確保したうえで、業者の到着を待つのが最も安全です。
Q5. ガス会社を呼ぶほどではない気がします。それでも連絡したほうがいいですか?
A. はい。少しでも異常を感じたら、連絡するのが正解です。
ガス会社は24時間体制で緊急対応を行っており、通報内容をもとに安全確認や現場点検を実施します。
「気のせいかも」と判断して放置することが、事故につながるケースもあります。
まとめ:ガスのにおいを感じたら“迷わず連絡を”
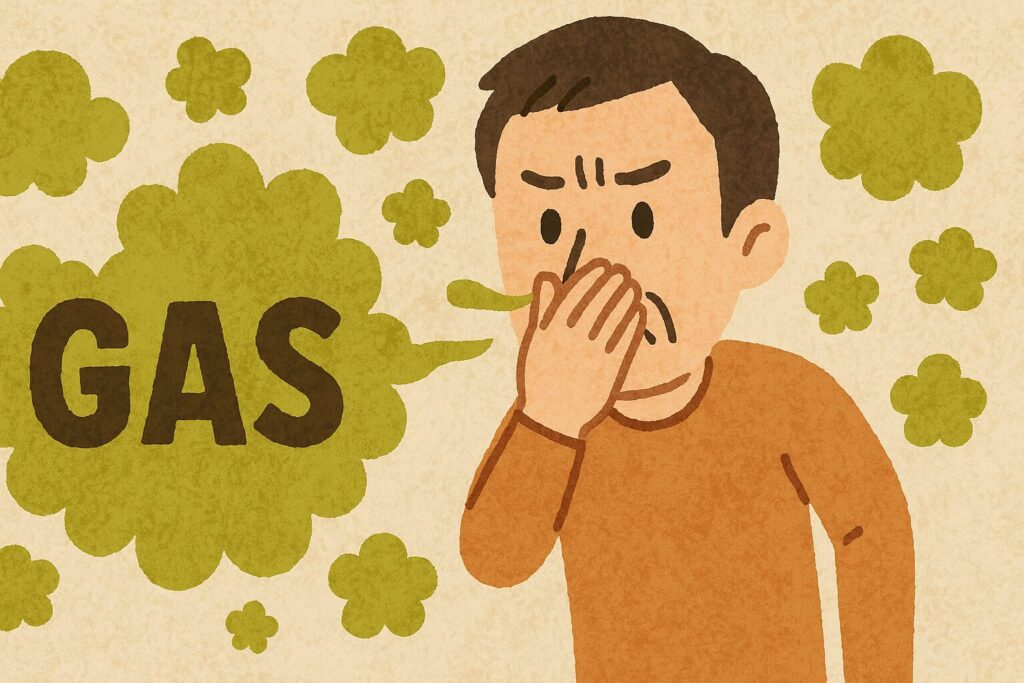
ガスのにおいは、決して「気のせい」ではありません。
都市ガス・LPガスともに、もともと無臭のガスに安全のための付臭剤(メルカプタン)が加えられています。
つまり、においを感じた時点で、ガスが想定外の場所に滞留しているというサインです。
多くの事故は、異変を感じながらも「少し様子を見よう」と使い続けたことが原因です。
火気を使わず、換気をして、ガス栓を閉め、できる限り安全を確保したうえでガス会社に連絡する。
この一連の行動を覚えておくだけで、危険を未然に防ぐことができます。
また、点火直後の一瞬のにおいなど、心配のいらないケースもありますが、「長く残る」「前より強く感じる」「警報器が反応する」といった状況では、ためらわず相談してください。
ガス会社は24時間体制で安全確認を行っており、早めの通報こそが最も確実な安全策です。
連絡先についても緊急事態に備えて、見えるところに掲示しておくのがいいでしょう。
日常の中でふと感じたにおいが、万一の前触れであることもあります。
迷ったときほど、“自分で判断しない”という意識が、家庭の安全を守ります。
物価高の今だからこそ、「ガス代だけは放置しない」選択を
ガス料金が高いと思う今だからこそ、ぜひ一緒に見直しておきたいのがLPガスそのものの契約内容です。
LPガスの料金は各ガス会社で設定しているものなので、どこのガス会社が一番安いか知りたくはありませんか?
食費・電気代・日用品…
何もかも値上がりしている今、契約を変えるだけで下がる可能性がある支出を見逃すのは、正直もったいない選択です。
「長年同じ業者だから安心」=「料金が適正」とは限りません。
実際に見直した結果、年間1万円〜2万円以上安くなった家庭も多数あります。
実は今、無料・匿名感覚でお住まいの地域に合った適正価格のガス会社をまとめて比較・紹介してもらえる方法があります。
しかも
✔ しつこい営業なし
✔ 今の契約を無理に変える必要なし
✔ 合わなければ断ってOK
「安くなる可能性があるか」を確認するだけでも利用できます。
何もせずに高い料金を払い続けるより、まずは一度、今の料金が適正かどうかを確認してみませんか?
▼ 申し込みから切替までネットで完結【エネピ】

入力は最短1分
複数のLPガス会社を一括比較
面倒な交渉はすべてお任せ