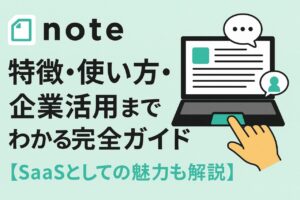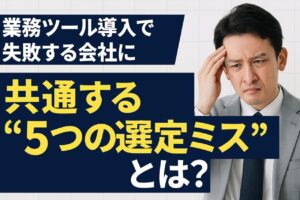便利なSaaS、でも「セキュリティ不安」で止まっていませんか?
業務効率化やリモートワークの普及により、SaaS(クラウド型業務ツール)の導入はすでに多くの企業で当たり前になりつつあります。
メール、チャット、勤怠、請求、CRM、プロジェクト管理……気づけば、業務のほとんどがSaaS上で完結している、なんて会社も多いはずです。
一方で、導入の検討段階になるとよく出てくるのが「セキュリティ面が不安で……」という声。たとえば、
- 「クラウド上のデータって安全なの?」
- 「社員が勝手にツールを使っていたらどうする?」
- 「万が一漏洩したらどう責任を取る?」
といった懸念が先立ち、導入が進まないケースは少なくありません。
そこで本記事では、SaaSセキュリティの基本から、導入前に確認すべきチェックリスト、そして企業側が取るべき対策までをわかりやすく整理しました。
「なんとなく不安」から「正しく備える」に変えて、安心してSaaSを活用できる状態を目指しましょう。
SaaSのセキュリティとは?オンプレミスとの違いを理解しよう

SaaSのセキュリティについて考えるとき、まず前提として理解しておきたいのが、「オンプレミス(自社運用)型」との根本的な構造の違いです。
ここを曖昧にしたまま議論すると、「クラウドってなんとなく不安」といった感覚論に陥り、冷静な判断ができなくなります。
たとえば、あなたの会社で使っている顧客管理ツールがあるとしましょう。
オンプレミス型なら、それは社内のサーバーにインストールされていて、社内ネットワーク経由でしかアクセスできません。
一方、SaaSの場合は、インターネットにさえつながっていればどこからでもアクセスできる状態になります。
この「アクセス経路の違い」や「管理の主体」が、セキュリティ設計・運用ルールにも大きく影響します。
以下は、代表的な違いを整理したものです。
| 観点 | オンプレミス型 | SaaS型 |
|---|---|---|
| データ保管場所 | 社内サーバ(自社管理) | クラウドサーバ(ベンダー管理) |
| セキュリティ責任範囲 | 原則、すべて自社 | ベンダーと利用企業の共同責任 |
| 保守・アップデート | 社内の情シスが対応 | ベンダーが自動で随時実施 |
| 導入スピード | 機器調達や構築に時間がかかる | ブラウザで即利用でき、柔軟に拡張可能 |
| カスタマイズ性 | 高いが専門知識が必要 | 制限はあるがテンプレ利用で効率的 |
つまりオンプレミスは、「手元で見える安心感」がある一方で、初期導入や保守の負担が大きくなります。逆にSaaSは、ベンダーの技術力と仕組みにセキュリティを委ねる構造なので、信頼できるサービスかどうかの見極めが非常に重要になります。
とはいえ、SaaSのすべてが「オンプレミスよりセキュリティが弱い」というわけではありません。
むしろ近年では、多くのSaaSベンダーが専門のセキュリティチームを抱え、最新の暗号化技術や攻撃検知システムを導入しています。
定期的な脆弱性診断や第三者認証(ISO27001、SOC2など)も標準装備になりつつあり、中小企業がオンプレミスで構築するより遥かに高レベルのセキュリティ環境が確保されているケースも珍しくありません。
ただし、SaaSには「便利すぎて見えづらくなるリスク」もあります。たとえば、社員が個人のアカウントで勝手に登録して使い始めたとしても、IT部門が把握できない状態(シャドーIT)が発生しやすくなります。
こうした特性を理解したうえで、「自社でコントロールすべき部分はどこか」「ベンダー任せにしてよい範囲はどこか」を見極めておくことが、SaaS時代のセキュリティ対策の出発点になります。
SaaSに潜む代表的な5つのセキュリティリスク

「SaaSは便利だけど、セキュリティがちょっと不安なんだよね」
——こんな声を、導入を検討する現場で耳にすることは少なくありません。
実際、SaaSは導入が簡単で、すぐに使い始められる反面、その手軽さゆえに起きやすいセキュリティトラブルも存在します。
とくに中小企業の場合、「ITに詳しい人が社内にいない」「管理ルールが曖昧なまま運用が始まってしまう」といった背景もあって、知らないうちにリスクを抱えていることが多いのが実情です。
以下では、SaaSを利用するうえで特に注意すべき代表的なリスクを5つ取り上げます。
どれも実際に多くの企業で問題となった事例があるものばかりです。
1. アカウント乗っ取り
SaaS利用で最も多く見られるトラブルが「アカウントの不正アクセス」です。
特に次のようなケースは、リスクが高まります。
- パスワードの使い回し(業務アカウントで個人と同じパスワードを使っている)
- 「123456」「password」など推測されやすい弱いパスワードの設定
- 二要素認証(2FA)の未導入
一度ログイン情報が漏れると、メール・ファイル・顧客情報など、SaaSに保存されたデータが丸ごと抜かれてしまう危険があります。
「誰かが見ているかもしれない」という前提で、アクセス管理を強化する必要があります。
2. シャドーITの増加
「とりあえず無料で使えるから導入してみた」
——この“手軽さ”が、SaaS普及を加速させた最大の理由でもありますが、同時に大きな落とし穴にもなり得ます。
情報システム部門や上長の承認を得ず、現場レベルで勝手にSaaSを使い始める状態を「シャドーIT」と呼びます。これは、以下のようなリスクを孕みます。
- 管理者が把握していないツールに業務データが蓄積される
- アカウントの削除漏れによって、退職者がログインできる状態が続く
- 誰が何にアクセスしているか不明瞭になり、事故の温床となる
SaaS導入の自由度が高まるほど、統制とルール整備の重要性も高まります。
3. データ共有設定ミス
GoogleドライブやBoxなど、ファイル共有系のSaaSで特に注意したいのが「共有設定の誤り」です。
- 「リンクを知っていれば誰でも閲覧できる」設定のまま、社外に送ってしまった
- 社員個人が外部にフォルダごと共有していた
- 編集権限を必要以上に広く与えていた
こうした“うっかり設定”は、誰にでも起こり得ます。特にテレワーク環境では、「誰とどこまで共有されているのか」を管理者が把握しきれないケースも多く、内部ミスからの情報漏洩リスクが高まっています。
4. サービス停止リスク
クラウドサービスである以上、ベンダー側の障害やシステムトラブルは避けられません。
- ベンダーのシステム障害で数時間使えなかった
- メンテナンス期間が長引き、業務に支障が出た
- 利用していたSaaSが急にサービス終了を発表した
SaaSは「自社の管理下にない」点が最大の特徴であり、逆に言えば、何かあっても“手が出せない”というリスクも伴います。
そのためには、以下のような事前確認が重要です:
- 障害発生時の連絡体制・サポート手段
- データのエクスポート方法(他サービスへの移行が可能か)
- バックアップ頻度とデータ復旧までのスピード
5. ベンダー体制の甘さ
すべてのSaaSベンダーが、同じレベルのセキュリティ体制を備えているわけではありません。
特に、次のような点には注意が必要です。
- 第三者認証(ISO/IEC 27001、SOC2など)を取得していない
- セキュリティポリシーが公開されていない、または内容が曖昧
- 過去に情報漏洩事故などが起きているが、再発防止策が明示されていない
導入の際は、「価格」や「機能」だけで判断せず、セキュリティ体制や過去の実績までチェックする姿勢が必要です。ベンダー選びは、単なるサービス選定ではなく、「パートナー選び」と考えた方が失敗が少なくなります。
主なSaaSベンダーのセキュリティ対策一覧
とはいえ、すべてのSaaSがリスクだというわけではありません。
むしろ、多くの有力SaaSベンダーは、強固なセキュリティ体制を築いています。導入検討の際は、こうした「ベンダー側の対応力」をしっかりチェックすることが重要です。
下記は、信頼できるSaaSが一般的に実装しているセキュリティ対策の代表例です。
| セキュリティ対策項目 | 内容例 |
|---|---|
| データ暗号化 | 通信時・保存時の暗号化(SSL/TLS、AESなど) |
| アクセス権限管理 | ロールベースの制御、閲覧権限の制限 |
| 二要素認証(2FA) | ID+スマホ認証、メール認証など |
| ログ管理・監査証跡 | 操作履歴の取得・保存、監査ログの保持 |
| 脆弱性診断・外部テスト | 定期的なペネトレーションテスト |
| 認証取得 | ISO/IEC 27001、SOC2、ISMS などの第三者認証 |
これらの内容は、SaaSの公式サイトやホワイトペーパー、導入資料などで開示されていることが多いため、必ず確認しておきましょう。
利用企業が行うべきセキュリティ対策
どれだけSaaSベンダー側が万全なセキュリティ対策を講じていても、それを使う側が無防備では意味がありません。実際、SaaS関連のセキュリティ事故の多くは、「ツールそのものの脆弱性」ではなく、社内の運用体制やルールの甘さが原因になっています。
たとえば、「退職者のアカウントが削除されず放置されていた」「ファイル共有リンクの設定ミスで外部に機密情報が漏れた」など、“ちょっとした見落とし”から深刻なトラブルに発展するケースは少なくありません。
とくに中小企業やスタートアップのように、情報システム専任の担当者がいない企業では、「最初から仕組みで守る」発想が非常に重要です。属人化させず、運用ルールとして誰でも扱える状態をつくることが、継続的なリスク管理につながります。
以下は、利用企業側で最低限取り組んでおくべき代表的なセキュリティ対策です。
● 強固なパスワードポリシーの策定と運用
「123456」や「password」といった安易なパスワードを未だに使っていませんか?
パスワードはセキュリティの最前線です。企業として以下のようなルールを整えましょう。
- 一定桁数以上(12文字以上)を必須とする
- 英数記号の組み合わせを義務化
- パスワードの定期変更
- 同一パスワードの使い回しを禁止
SaaSの管理者だけでなく、全社員がこの基準を理解し、守れる状態にすることが重要です。
● 二要素認証(2FA)の必須化
ユーザー名とパスワードに加えて、スマホやメールなど“もう1つの要素”で本人確認を行う仕組みが2FAです。
たとえパスワードが漏れても、ログインが防げるため、不正アクセスの防止に極めて有効です。
すでに多くのSaaSでは2FAに対応しているため、設定が可能なものは原則すべて有効化しましょう。
● SaaSの利用状況を一元管理するツールの導入
社員がいつ、どのSaaSを使っているかを把握できていない企業は意外と多く、「誰が、どこで、どんな情報にアクセスしているか」がブラックボックス化してしまいがちです。
こうした状況を防ぐために、**SaaS利用を可視化・管理するツール(例:HENNGE One、Okta、JumpCloudなど)**の導入が有効です。ID連携・シングルサインオン(SSO)機能なども併用することで、運用効率とセキュリティの両立が可能になります。
● 情報セキュリティに関する定期的な社内研修
どんなにシステムが整っていても、扱う人間の意識が低ければ意味がありません。
特にシャドーITや共有設定ミスなど、人為的なトラブルは教育による予防が最も効果的です。
年1回の形式的な研修ではなく、「事例ベースで考えるワークショップ形式」や「部門別の具体的な利用ケースを交えたハンズオン形式」など、実践的な教育スタイルを取り入れると定着率が高まります。
● 退職者のアカウント即時削除・定期的な棚卸し
人事異動や退職があっても、SaaSのアカウントがそのまま残っている企業は少なくありません。
これが不正アクセスや情報持ち出しの温床となります。
- 退職者のアカウントは原則当日中に無効化
- 部署異動時にもアクセス権限の見直しを実施
- 四半期ごとに全アカウントを棚卸して管理者と照合
こうした地道なメンテナンスこそが、継続的なセキュリティ維持の鍵です。
● ファイル共有・外部連携のルール策定
「誰とでも共有可能」なファイルリンクを使っていませんか?
クラウドストレージは便利ですが、共有の設定ミスがそのまま情報漏洩に直結します。
社内で以下のようなルールを整備しておきましょう。
- 共有は社内メンバー限定が原則
- 社外共有時は承認フローを必須化
- 外部サービスとの連携(API利用など)は管理者が承認
共有ルールを明文化し、社内ポータルやガイドラインとして常に確認できるようにするのがポイントです。
このように、SaaSセキュリティ対策は「ツールに任せきり」ではなく、「使う人間」と「運用体制」のバランスで成り立ちます。
特別なITスキルがなくても、社内全体でセキュリティ意識を高めることは十分可能です。
逆にそこを怠ると、どれだけ高機能なSaaSを導入しても、リスクは残ったままになります。
【保存版】SaaS選定時に確認すべきセキュリティチェックリスト

「このSaaS、便利そうだけど…セキュリティは大丈夫なのか?」
いざ導入を検討する段階になると、そうした漠然とした不安が出てくるのは自然なことです。
しかし、セキュリティは“感じるもの”ではなく“確認するもの”。
明確な基準と質問リストを持っておくことで、「なんとなく不安」から「納得して選べる」状態に変わります。
以下に、SaaS導入時に必ずチェックしておきたい6つの観点と、具体的な質問例を整理しました。
ツールの選定担当者・情シス・経営層への説明資料としても活用できる保存版です。
| チェック項目 | 質問例・確認内容 | チェックポイントの解説 |
|---|---|---|
| 暗号化対応 | 通信・保存時ともに暗号化されているか? | 通信中のSSL/TLSや、保存時のAES暗号など。明記されていない場合は導入を慎重に。 |
| 認証方式 | 2FA・SSO・IP制限に対応しているか? | 二要素認証やシングルサインオンがあれば、なりすましリスクを大幅に低減可能。 |
| ログ・監査証跡 | 操作ログを確認・保存できる仕組みがあるか? | 誰が・いつ・何をしたかが記録されていることで、万一の事故時も追跡できる。 |
| データ保管先 | 日本国内または信頼性ある地域のデータセンターか? | データの物理的保管場所は法律・規制に直結。海外クラウドは特に確認を。 |
| 第三者認証取得 | ISO27001、SOC2などを取得しているか? | セキュリティ管理体制の客観的指標。取得していれば一定の水準は担保される。 |
| 障害・停止時の対応 | 復旧手順や連絡体制、バックアップ頻度は明記されているか? | 障害発生時に業務が止まらないよう、事前に対応ポリシーを確認。 |
選定時のポイント
- 「よくある質問」や「セキュリティホワイトペーパー」の有無も要チェック
しっかりしたベンダーほど、こうした情報公開に積極的です。 - 問い合わせ対応のスピード・丁寧さも判断材料に
技術的な質問をした際、すぐに明確な回答が返ってくるかどうかも、信頼性を測るうえで大切な指標です。 - すべてを満たしていなくても、「なぜ未対応なのか」を説明できるかが重要
すべてのSaaSが完璧な対応をしているとは限りません。重要なのは、ベンダーがリスクをどう捉え、どう対応しているかを説明できる体制にあるかです。
このチェックリストは、SaaS選定の「セキュリティ目線での最低限の物差し」です。
導入を焦る前に、このリストをベンダーにぶつけてみてください。
それだけで見えてくることがきっとあると思います。
安全に導入を進めるための相談先・支援サービス
「うちにはITに詳しい人がいないんだよね」
「セキュリティって、正直どこまで考えればいいのかわからない……」
——そんなふうに感じたことがあるなら、外部のプロに相談することは、決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、社内に専門家がいないのが普通だからこそ、知見のある第三者と組むことが、SaaS導入を失敗させない最短ルートになります。特にセキュリティに関しては、自己流の判断が命取りになる場面もあるため、初期段階から「聞ける相手」がいると非常に心強いものです。
ここでは、SaaS導入やセキュリティ対策を支援してくれる外部パートナーの種類と役割を整理しておきましょう。
● IT導入支援事業者
中小企業のIT化を支援する国の認定制度(IT導入補助金など)にも関わっており、
コスト面も含めて導入を伴走してくれる存在です。
- SaaS導入の初期設計支援
- 補助金申請のサポート
- 操作マニュアルの作成 など
「まずどこから始めればいいかわからない」という方にとって、非常に頼れる存在です。
● セキュリティ診断企業
「本当にこの運用で大丈夫か?」を確認したいときは、
客観的な診断をしてくれるセキュリティ専門企業に相談しましょう。
- 現在のIT環境の脆弱性診断
- 情報漏洩リスクの洗い出し
- 社内セキュリティポリシーの整備支援 など
定期的な“健康診断”のような位置づけで活用すると、トラブルの未然防止につながります。
● SaaS導入コンサルティング企業
複数のSaaSを比較・選定する段階や、社内展開の設計で悩んでいる場合は、
SaaS導入支援に特化したコンサル企業が心強い味方になります。
- 自社業務に合ったツールの選定
- ベンダーとの契約・運用設計のサポート
- 社内教育・運用フロー整備の支援 など
一時的なアドバイスだけでなく、「導入後の活用フェーズまで一緒に考えてくれる」のが特徴です。
長く付き合える“相談相手”を持っておこう
一度だけの相談で終わるのではなく、継続的に信頼できるパートナーを持つことが、企業の“情報資産”を守る上で非常に重要です。
特にセキュリティは、導入時だけではなく運用が始まってからも変化し続ける領域。
ベンダー任せ・一人任せにせず、「困ったときに聞ける相手がいる状態」を早めにつくっておくことが、安心してSaaSを使い続けるための基盤になります。
FAQ(よくある質問)
Q1. SaaSのセキュリティはオンプレミスより劣るのですか?
A. 一概には言えません。
確かに「社内に置いておけば安全」という感覚を持ちやすいオンプレミスですが、実際には管理の手間やアップデートの遅れがリスクになることもあります。
一方でSaaSは、専門のセキュリティチームによる運用・監視や、最新技術の即時反映が可能です。正しく選定・運用されたSaaSであれば、オンプレミスより高いセキュリティを維持できるケースも多々あります。
Q2. 無料のSaaSでも業務で使っていいのでしょうか?
A. 注意は必要です。
無料プランでも暗号化や2FAに対応しているサービスは増えていますが、保証範囲やサポート体制、障害時の対応スピードには限界がある場合が多いです。
また、個人向けに設計されたツールを業務で使うと、法的な責任や情報管理の観点で問題になる可能性もあるため、業務利用を想定したプラン・契約形態かどうかを確認しましょう。
Q3. 社員の“勝手なSaaS利用”(シャドーIT)を防ぐには?
A. 可視化と教育の両面から対策が必要です。
まずはID管理ツールやSSO(シングルサインオン)を導入し、「誰が・どのサービスを・いつ使っているか」を把握できる体制を整えましょう。
加えて、定期的なセキュリティ研修や社内ルールの明文化を通じて、「なぜ申請が必要なのか」「情報資産をどう守るのか」を浸透させることが、最も確実な抑止力になります。
Q4. セキュリティ認証(ISO27001、SOC2など)を取得していれば安心ですか?
A. 安心材料の一つではありますが、それだけで万全とは限りません。
認証の取得は、一定水準の体制・管理ができている証拠にはなります。ただし、実際の運用ルールや社内設定(共有範囲・権限・ログ管理など)も同じくらい重要です。
認証がある=信頼できる、ではなく、「認証をどう活かして運用しているか」に目を向けましょう。
Q5. 中小企業でもセキュリティ対策は必要ですか?
A. むしろ中小企業こそ“最初から整える”意識が重要です。
「うちは狙われないから大丈夫」と思っていませんか? 実際は、セキュリティ体制の甘さを狙った“無差別攻撃”の被害に遭う企業の多くが中小規模です。
人的リソースが限られているからこそ、最初からルールと仕組みを整え、属人化せずに守れる状態をつくっておくことが、長期的なリスク軽減につながります。
最後に|セキュリティを「理由にしない」ために、正しく知ることから始めよう

「なんとなく不安だから、今はまだやめておこう」
その判断、もしかすると“何を知らないのかが分からない状態”が原因かもしれません。
実際、SaaSのセキュリティは専門的な用語や仕組みが多く、初めて導入を検討する企業にとってはとっつきづらいテーマです。
でも、本記事でご紹介してきたように、ポイントさえ押さえれば「確認すべきこと」は意外とシンプル。
暗号化の有無・認証方式・ログ管理・データ保管先・体制の透明性など、見るべき項目は明確にあります。
つまり、“わからないから怖い”を“わかって選べる”に変えることは、誰にでもできるということ。
そしてもうひとつ大事なのが、「安心して使うためには、自社側にも備えが必要」という視点です。
ルールの整備、社員教育、退職者管理、ID管理ツールの導入……。
こうした地道な積み重ねが、結果としてSaaSの強みを最大限に引き出す“安全な運用”につながります。
いま求められているのは、完璧なセキュリティ対策ではなく、必要なリスクを見極め、正しく備える力。
つまり、選ぶ力そのものです。
要点まとめ|SaaS導入とセキュリティの本質
- 不安の正体を言語化することで、必要な確認ポイントが見える
- ベンダーの対策に頼るだけでなく、自社の体制整備も重要
- 専門知識がなくても、最低限のチェックリストと支援パートナーで対応可能
- セキュリティは“止める理由”ではなく“前に進むための条件”として考える
- 選ぶ力=ビジネスを守る力であり、活かす力でもある
だからこそ、今の段階で「調べてみた」あなたの行動は、すでに第一歩を踏み出しています。
RE:SEARCH BASEは、そんな行動を“成果につなげるための知識と視点”を、これからも届けていきます。